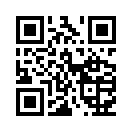民族的多様性の維持、二極化、そして階層化
2006年03月07日

 皆さんからの愛の1クリックが活力源です。よろしくね♪
皆さんからの愛の1クリックが活力源です。よろしくね♪おとといの記事「南島的季節感」は、追記へのトラックバック記事において「沖縄(以下、琉球列島全体を含む)以外の日本をなんと呼ぶか」という話題に発展した。
その中で、そもそも沖縄とそれ以外の日本を区別する必要があるのか、という問いが提示された。
最初私は、区別するのは琉球王国民の末裔としての民族意識ではないかと考えた。
それなら、このような意識をなくすのではなく、むしろ他の地域の人に理解を求めることが大切ではないかとコメントした。
日本人という国民としてまとまると同時に、その中に民族的多様性を認め互いの立場を尊重しあうべきではないかとも述べた。
しかし全体としては、沖縄とそれ以外の地域を区別することに慎重な意見が多かった。
多くの人が「ヤマト」、「本土」、「内地」に嫌悪感や違和感を抱いてることから、末裔たちが何気なく使うこれらの言葉ないしその根底にある区別に差別的な意識が含まれ得ることは、ほぼ明白といえるだろう。
しかしこれらの言葉や区別する思考を取り除いたとき、果たして民族意識は、民族の多様性は維持できるのだろうか?
トラックバックしてくださったTstsshihicaさんのコメントから、そのヒントを見つけた。
「確かに理解を求めるというのも、重要ですね。ただ、この意識が、沖縄にとって沖縄の問題を考えるとき、『わった~は違うからいいさぁ~』という逃げ理由付けに使われていないだろうかとふと思っています。」(Tstsshihicaさんのコメントより引用)
日本人全体に対して「わった~は違うから」と考えるのは、多様性の維持ではなく二極化ではないだろうか?
私が多様性ではないかと考えたものは多くの人にとって二極性と捉えられており、この両者は表裏一体なのだ。
私は多様性の維持は大切だと考えるが、二極化は日本人であることの否定、そして排他的な思考につながりやすいため(必ずではないが)、沖縄自体のために好ましくないと考える。
ウチとソト、自己と他者を区別することにはこのような危険な一面も含まれるのだということに気付かされた。
余談だが、その記事のコメントにもう1つ面白い言葉があったので、紹介させて欲しい。
「沖縄の中のマイノリティー?というと語弊があるかもしれませんが、その人々が、呼称に関してどう思うか?も気にしていかないといけないような気がしています。」(Tstsshihicaさんのコメントより引用)
沖縄の中のマイノリティー、これもまた忘れてはならない問題だ。
具体的には沖縄本島(および近隣のいくつかの島)以外の人間、歴史的には琉球王朝に従属していた島の人々だ。
私のふるさと奄美大島では一般に、「シマ」と「ヤマト」を区別するときは自分たちは沖縄の側に属するが、「オキナハ」という言葉を使うときにはそこに自分たちは属さない。
周辺諸島の1つになるのだ。
最初それは奄美が鹿児島県だからだと思っていたが、宮古島出身の後輩が「沖縄の人は、、、」と本島の人間について語るのを見て宮古も奄美と同じ立場にあるのだと感じた。
さらにある人類学の先生から、「自分のことをウチナーンチュだと思っているのは本島出身者だけだよ」と聞かされ、沖縄とその周辺諸島という二項対立の概念があることを知った。
周辺諸島をひとくくりにするような概念は聞いたことがないから、おそらく「シマンチュ(奄美ではもっぱらこれが使われる)」、「ミャークンチュ」、「ヤイマンチュ」のような言葉には各々の島と他の琉球列島という二項対立が含まれているのだろう。
各々の島と沖縄本島の間に対立があるのかどうかは知らないけれど、これについてはもっと勉強してから語ろう。
さらに余談だが、私が首里に住んでいるときも名護に住んでいるときも親戚から「あんたはナーファンチュだね」と言われた。
もしかすると周辺諸島の人にとって沖縄イコール那覇なのかもしれない。
沖縄とそれ以外の地域という区別は従来の多様性の維持であり、二極化でもあり、さらに二極化したうちの一方において二極化が起きて、、、という階層化でもあるのだ。
追記 Tstsshihicaさん、知り合ったばかりなのに思いっきりネタに使わせていただきました。図々しくて申し訳ないです_(._.)_それにしても余談の長い文章だね^^
Posted by jumechi at 23:43│Comments(13)
│沖縄の話
この記事へのコメント
はじめまして、最近、ブログをはじめた者です。
今日は、すごくシリアスな話題でしたね。でも、こういうことは一人ひとりに1度は真剣に考えてほしいことです。
ここは沖縄・日本です。しかし、文化の側面からみると明らかに「日本文化」とは違う点があります。もちろん沖縄だけではなくて、九州も四国も関西も関東も東北も北海道もその地域ごとの近似文化があるわけで・・・
「九州と東北ってここは似てるのねぇ。不思議ねぇ。やっぱり遠く離れててもここは日本なのねぇ。でも、ここは全然違うわねぇ。不思議ねぇ。遠く離れていると、こんなに違ってくるものなのねぇ」って感じ? 無理やり例えてみました。
要は、「分ける」必要はないのです。
ただそこに、地域ごとの文化に「違い」がある
ということでしかないということです。
いままで政治的に社会学的に いろいろな分け方や呼び方があります。
それも、あまり人々の生活や思想にとっては、あまり意味を持たないよう
な気がします。
ん~何が言いたかったのかわからなくなってきたぁ・・・
すみません、支離滅裂ですねぇ。 しかも長くなってしまいました。
一番言いたいことは、
このblogを私のblogにリンクに貼っていいですか?
ということでした。 お返事まってます!
今日は、すごくシリアスな話題でしたね。でも、こういうことは一人ひとりに1度は真剣に考えてほしいことです。
ここは沖縄・日本です。しかし、文化の側面からみると明らかに「日本文化」とは違う点があります。もちろん沖縄だけではなくて、九州も四国も関西も関東も東北も北海道もその地域ごとの近似文化があるわけで・・・
「九州と東北ってここは似てるのねぇ。不思議ねぇ。やっぱり遠く離れててもここは日本なのねぇ。でも、ここは全然違うわねぇ。不思議ねぇ。遠く離れていると、こんなに違ってくるものなのねぇ」って感じ? 無理やり例えてみました。
要は、「分ける」必要はないのです。
ただそこに、地域ごとの文化に「違い」がある
ということでしかないということです。
いままで政治的に社会学的に いろいろな分け方や呼び方があります。
それも、あまり人々の生活や思想にとっては、あまり意味を持たないよう
な気がします。
ん~何が言いたかったのかわからなくなってきたぁ・・・
すみません、支離滅裂ですねぇ。 しかも長くなってしまいました。
一番言いたいことは、
このblogを私のblogにリンクに貼っていいですか?
ということでした。 お返事まってます!
Posted by Miao at 2006年03月08日 00:38
いえいえ、jumechiさん、私のブログのネタを取り上げてくださり
ありがとうございます。コメントまで引用していただき、嬉しい限りです。
「二極化」という言葉は、あるほどなぁ~と思いました。
自分でもいろいろと考えて、まとめてみたいと思います。
これからもよろしくお願いします!
ありがとうございます。コメントまで引用していただき、嬉しい限りです。
「二極化」という言葉は、あるほどなぁ~と思いました。
自分でもいろいろと考えて、まとめてみたいと思います。
これからもよろしくお願いします!
Posted by Tstsshihica at 2006年03月08日 01:35
びみょーな問題ですな。
これは国外で生まれた日本人2世、3世...をどのように呼ぶかと
ゆー問題にもつながりませんかね...?
すなわち、2世の我輩は日本人でもなければボリビア人でもなく、中間に
属するので日系人とゆーことになるようです。
まーしかし、テレビなどで「ガイジン」はおやめなさいな。 ニッポンジンだって一歩国外に出れば外人ですよ。
これは国外で生まれた日本人2世、3世...をどのように呼ぶかと
ゆー問題にもつながりませんかね...?
すなわち、2世の我輩は日本人でもなければボリビア人でもなく、中間に
属するので日系人とゆーことになるようです。
まーしかし、テレビなどで「ガイジン」はおやめなさいな。 ニッポンジンだって一歩国外に出れば外人ですよ。
Posted by neko at 2006年03月08日 10:29
難しい問題ですね。
自分も奄美に来て、鹿児島を「本土」と呼ぶようになり、
地元の人は「内地」と呼ぶ。あるいは「鹿児島」と。
考えてみれば、奄美も鹿児島県。こちらで言う鹿児島は
島ではない鹿児島全部のこと。
そういえば、今度の選抜、「離島で初めて甲子園出場」と言われた
石垣商業…沖縄本島があって、離島なんだなあと。本当に、鹿児島県における奄美群島と同じ立場なんだなと思いました。
何だかまとまりのない文になってしまいました、何が言いたいのか分からなくなってきた。ごめんなさい。
自分も奄美に来て、鹿児島を「本土」と呼ぶようになり、
地元の人は「内地」と呼ぶ。あるいは「鹿児島」と。
考えてみれば、奄美も鹿児島県。こちらで言う鹿児島は
島ではない鹿児島全部のこと。
そういえば、今度の選抜、「離島で初めて甲子園出場」と言われた
石垣商業…沖縄本島があって、離島なんだなあと。本当に、鹿児島県における奄美群島と同じ立場なんだなと思いました。
何だかまとまりのない文になってしまいました、何が言いたいのか分からなくなってきた。ごめんなさい。
Posted by tokorin at 2006年03月08日 20:47
Miaoさん、
リンク大歓迎ですよ!
良かったら相互リンクしませんか?
「分ける」という言葉も人によって少しずつ意味が違ったりするとは思いますが、「違い」に気付くことは大切でしょうね。
違いを受け入れたくない場合は距離を置くほうが平和でいられるんだろうし、違いを楽しめるなら、きっと素敵な関係を築けると思います。
僕は言語専門ではないけれど、言葉には興味があるしモノカキだった頃もあるので、たまに言語ネタやりましょう♪
ところでMiaoさん、以前にお会いしたことありませんか?
あなたのブログを拝見して、そんな気がしました。
リンク大歓迎ですよ!
良かったら相互リンクしませんか?
「分ける」という言葉も人によって少しずつ意味が違ったりするとは思いますが、「違い」に気付くことは大切でしょうね。
違いを受け入れたくない場合は距離を置くほうが平和でいられるんだろうし、違いを楽しめるなら、きっと素敵な関係を築けると思います。
僕は言語専門ではないけれど、言葉には興味があるしモノカキだった頃もあるので、たまに言語ネタやりましょう♪
ところでMiaoさん、以前にお会いしたことありませんか?
あなたのブログを拝見して、そんな気がしました。
Posted by jumechi at 2006年03月08日 23:07
Tstsshihicaさん、
トラバいただいた記事はとても刺激的でした。
いつもならネタとしてストックしておくのですが、今回は印象が鮮明なうちにまとめてみたくなり早速使わせていただきました。
勢いにまかせて書いたので少し荒削りですが、そのうちもっと練ったものを書きたいと思います。
トラバいただいた記事はとても刺激的でした。
いつもならネタとしてストックしておくのですが、今回は印象が鮮明なうちにまとめてみたくなり早速使わせていただきました。
勢いにまかせて書いたので少し荒削りですが、そのうちもっと練ったものを書きたいと思います。
Posted by jumechi at 2006年03月08日 23:14
nekoさん、
「日系××世」は、慎重に扱うべき言葉ですよね。
もともと送出国である日本がつけた名前なので誤解も多く含まれると思います。
例えば、ボリビアにおける戦前移住グループの2世と戦後移住グループのそれとでは一般に意識や立場が違うし、同じ言葉で表すのは不自然でしょ?
僕個人としては各個人の意識によって何人であるか決定されるべきだと考えていますが、実際には社会がそれを認めない場合が多いですよね。
だから、日系社会の内部から自分たちの呼称を創るのが理想かなと思います。
「日系××世」は、慎重に扱うべき言葉ですよね。
もともと送出国である日本がつけた名前なので誤解も多く含まれると思います。
例えば、ボリビアにおける戦前移住グループの2世と戦後移住グループのそれとでは一般に意識や立場が違うし、同じ言葉で表すのは不自然でしょ?
僕個人としては各個人の意識によって何人であるか決定されるべきだと考えていますが、実際には社会がそれを認めない場合が多いですよね。
だから、日系社会の内部から自分たちの呼称を創るのが理想かなと思います。
Posted by jumechi at 2006年03月08日 23:31
tokorinさん、
おっしゃりたいこと、よく解りますよ^^
僕だっていまだに「鹿児島」という地名を奄美を含めずに使ってますから。
沖縄県に住みはじめた頃、「離島」とは沖縄本島以外の島のことだと知ってびっくりしました。
行政上の地名と人々が使う地名とでは意味が微妙に違うようですね。
おっしゃりたいこと、よく解りますよ^^
僕だっていまだに「鹿児島」という地名を奄美を含めずに使ってますから。
沖縄県に住みはじめた頃、「離島」とは沖縄本島以外の島のことだと知ってびっくりしました。
行政上の地名と人々が使う地名とでは意味が微妙に違うようですね。
Posted by jumechi at 2006年03月08日 23:41
nekoさんへ再び、
さっき書き忘れたんですが、「日系」の定義は日本社会においても統一されてないようです。
しかも多くの人が自分の頭にある「日系」と法律上の「日系」を混同していることに気付いてない。
私自身も法律上の厳密な定義は知らないんですが、今のところ関心はないので調べてません。
やはり「日系社会」による意思表明や世界の日系社会どうしのコミュニケーションは必要だと思います。
私にそのお手伝いができれば、とても光栄に思います。
さっき書き忘れたんですが、「日系」の定義は日本社会においても統一されてないようです。
しかも多くの人が自分の頭にある「日系」と法律上の「日系」を混同していることに気付いてない。
私自身も法律上の厳密な定義は知らないんですが、今のところ関心はないので調べてません。
やはり「日系社会」による意思表明や世界の日系社会どうしのコミュニケーションは必要だと思います。
私にそのお手伝いができれば、とても光栄に思います。
Posted by jumechi at 2006年03月08日 23:51
この問題,多分,政治,経済,文化,自然,地理,民族等,論点になっている局面ごとに分けて考えることができるんじゃないかと思います。
たとえば,奄美群島だと,政治的には,鹿児島県ですが,文化的には,鹿児島本土とは全く違い,しかも,奄美群島の中でも,奄美大島,徳之島,沖永良部,与論etc.とそれぞれが全く違う個性豊かな文化を持っていますよね。
と,分けて考え出すと,それぞれの局面で,本当に多様で,それだけで一冊の本になってしまいそうな気がして...
東京から奄美大島へ引っ越してきた私は,奄美大島で生まれ育った人以上に,「奄美大島」という存在の独自性を痛感しつつある今日この頃です。
ところで,道州制の議論って,沖縄でどんな風に捉えられています?
先日の地元紙で,与論では,九州ブロックではなく,沖縄ブロックへ入れて欲しいという議論が少し出始めているようなことが書かれていました。
奄美大島ではというと,私の知る限り,そもそも道州制の議論にあまり関心がないし,わずかに関心がある人も,奄美大島が沖縄ブロックへ入るなんてことは微塵も考えていないようです。
この当たりにも,与論と奄美大島の地理的,経済ブロック的な相違点を感じます。
P.S. 先日のjumechiさんのコメント,全然不愉快になんか感じてませんよ(^_-)
たとえば,奄美群島だと,政治的には,鹿児島県ですが,文化的には,鹿児島本土とは全く違い,しかも,奄美群島の中でも,奄美大島,徳之島,沖永良部,与論etc.とそれぞれが全く違う個性豊かな文化を持っていますよね。
と,分けて考え出すと,それぞれの局面で,本当に多様で,それだけで一冊の本になってしまいそうな気がして...
東京から奄美大島へ引っ越してきた私は,奄美大島で生まれ育った人以上に,「奄美大島」という存在の独自性を痛感しつつある今日この頃です。
ところで,道州制の議論って,沖縄でどんな風に捉えられています?
先日の地元紙で,与論では,九州ブロックではなく,沖縄ブロックへ入れて欲しいという議論が少し出始めているようなことが書かれていました。
奄美大島ではというと,私の知る限り,そもそも道州制の議論にあまり関心がないし,わずかに関心がある人も,奄美大島が沖縄ブロックへ入るなんてことは微塵も考えていないようです。
この当たりにも,与論と奄美大島の地理的,経済ブロック的な相違点を感じます。
P.S. 先日のjumechiさんのコメント,全然不愉快になんか感じてませんよ(^_-)
Posted by vagabond67 at 2006年03月09日 00:24
んーとね...確か資料が...あったった。
2001年にニューヨークで行われた第11回汎米日系大会(COPANI)で
提出された「日系人」の規定(案)は:
「自分は、日本文化を継承する、あるいは分かち合う意識を有する者」
だそうです。
沖縄人の規定には「ウチナー口の継承」が入るのでしょうね...
2001年にニューヨークで行われた第11回汎米日系大会(COPANI)で
提出された「日系人」の規定(案)は:
「自分は、日本文化を継承する、あるいは分かち合う意識を有する者」
だそうです。
沖縄人の規定には「ウチナー口の継承」が入るのでしょうね...
Posted by neko at 2006年03月09日 22:19
vagabond67さん、
奄美群島の島々は本当に個性的ですよね。
奄美育ちの人以上に奄美の独自性を痛感するということ、よく解ります、私も沖縄で同じことを体験しましたから(笑)
実際この数ヶ月間で多くの奄美関係ブログに出会いその魅力を再認識しましたが、ほとんどが奄美育ちでない人のブログでした。
それぞれの島の多様性を理解したら、好き嫌いは出てきても上下関係は出てこないと思うんですよ。
こういった多様性をできるだけ解りやすい形で表現できたらいいですね。
道州制、そういえば私自身も久しぶりに思い出しました。
私の周辺でもあまり関心は高くないようです。
地域の多様性の維持という観点から、連邦制のような国家のあり方はもっと議論されていいと思いますよ。
奄美が九州ブロックへ行くとしたら、少し寂しいですね。
道州制がスタートする前にはかなり綿密に議論されるでしょうから、その中で自然、文化、地理、経済などあらゆる側面から奄美の価値を考えて欲しいですね。
学生の頃、与論に住む知人がよく週末を利用して名護や那覇に出てきてましたね。
奄美よりずっと近いし、那覇辺りに行けばちょっとした都会の空気を味わえますからね♪
奄美群島の島々は本当に個性的ですよね。
奄美育ちの人以上に奄美の独自性を痛感するということ、よく解ります、私も沖縄で同じことを体験しましたから(笑)
実際この数ヶ月間で多くの奄美関係ブログに出会いその魅力を再認識しましたが、ほとんどが奄美育ちでない人のブログでした。
それぞれの島の多様性を理解したら、好き嫌いは出てきても上下関係は出てこないと思うんですよ。
こういった多様性をできるだけ解りやすい形で表現できたらいいですね。
道州制、そういえば私自身も久しぶりに思い出しました。
私の周辺でもあまり関心は高くないようです。
地域の多様性の維持という観点から、連邦制のような国家のあり方はもっと議論されていいと思いますよ。
奄美が九州ブロックへ行くとしたら、少し寂しいですね。
道州制がスタートする前にはかなり綿密に議論されるでしょうから、その中で自然、文化、地理、経済などあらゆる側面から奄美の価値を考えて欲しいですね。
学生の頃、与論に住む知人がよく週末を利用して名護や那覇に出てきてましたね。
奄美よりずっと近いし、那覇辺りに行けばちょっとした都会の空気を味わえますからね♪
Posted by jumechi at 2006年03月09日 23:20
nekoさん、
情報ありがとうございます。
なるほど、やはり本人の意識に委ねられるわけですか?
このような議論が今後も継続されることを願っています。
私もいつの日か参加できるといいな。
情報ありがとうございます。
なるほど、やはり本人の意識に委ねられるわけですか?
このような議論が今後も継続されることを願っています。
私もいつの日か参加できるといいな。
Posted by jumechi at 2006年03月09日 23:23